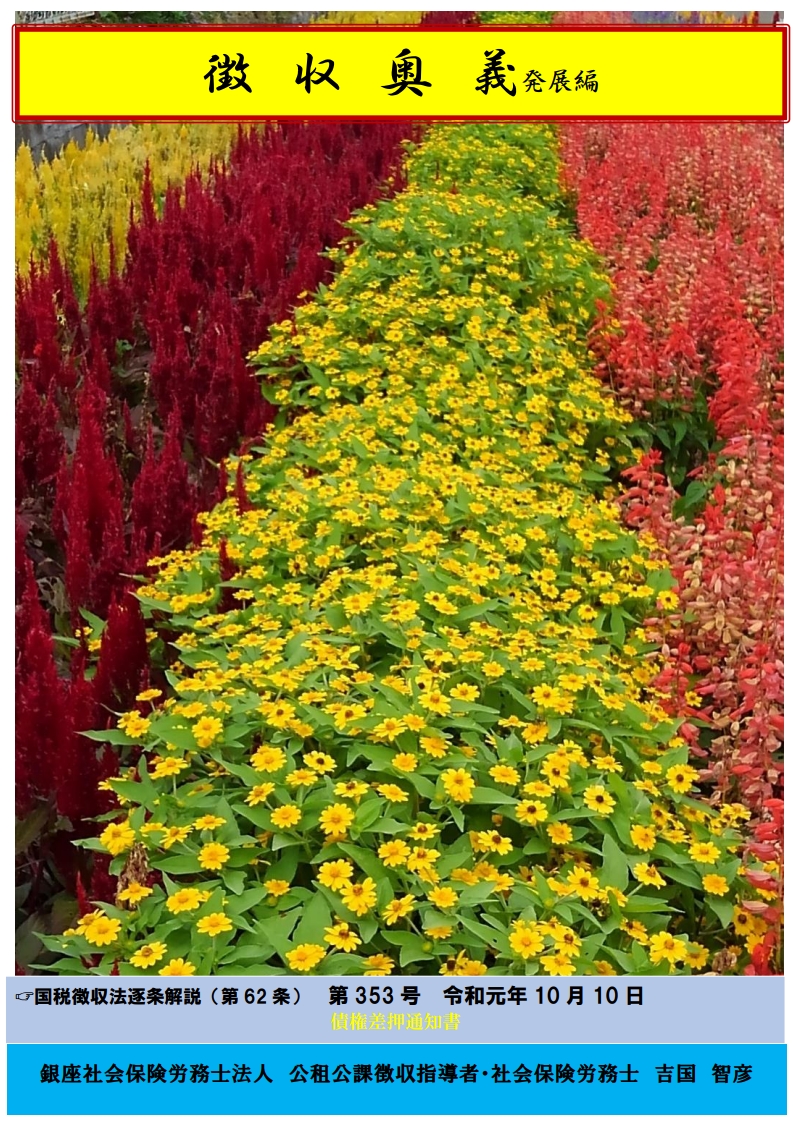181件中3件を表示しています。このページは51/61ページです。
滞納処分の実務書:相殺の意思表示
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義355号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
前号から徴収職員の知識の中でも高度、かつ、最重要の相殺についての解説が進行しています。
今号では、相殺の意思表示について、相殺の効力が生じる日、意思表示は誰に対して行うべきものか、債権を差押えし、第三債務者が相殺の意思表示をしてきたときで、それが正当であるときの差押えの効力がなくなる日等について解説を行っています。
主な内容は次のとおりです。
1 意思表示
2 相殺の効力発生時期
3 相殺の意思表示
4 延滞金の減免
5 消滅時効にかかった債権による相殺
掲載判例
最一判昭36.4.20(民集15-4-774)
最三判昭39.10.27(民集18-8-1801、金法394-11)
最三判昭40.7.20(集民79-893、金法417-12)
最一判昭51.3.4(民集30-2-48)

滞納処分の実務書:相殺
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義354号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
徴収職員の知識の中でも高度で、かつ、最重要の部類に入る相殺の解説です。分量が多く、数回に分けて解説します。
まずは、基礎的事項と預金債権を差し押さえしたときの一般的な内容についてです。
9月刊行図書である「自治体徴収職員のための債権差押えの実務」が昨年刊行の供託解説書と並んで、渋谷ジュンク堂書店に陳列されている写真を表紙としています。書店に行かれたときは、ご覧になってください。
主な内容は次のとおりです。
1 相殺という定型句
2 相殺制度を知らない同士
3 預金債権差押えと相殺の構図
4 相殺用語
5 相殺制度の存在意義
6 相殺できる場合
7 銀行の預金債権差押えにおける相殺
8 制限説の解釈
9 無制限説の解釈
10 預金に係る相殺の整理
11 相殺できない場合・できる場合
12 反対債権があるときの預金債権差押え
掲載判例
大判昭9.9.15(民集13-1-839)
最大判昭39.12.23(民集18-10-2217)
最大判昭45.6.24(民集4-6-587、訟務16-8-830、判時595-29)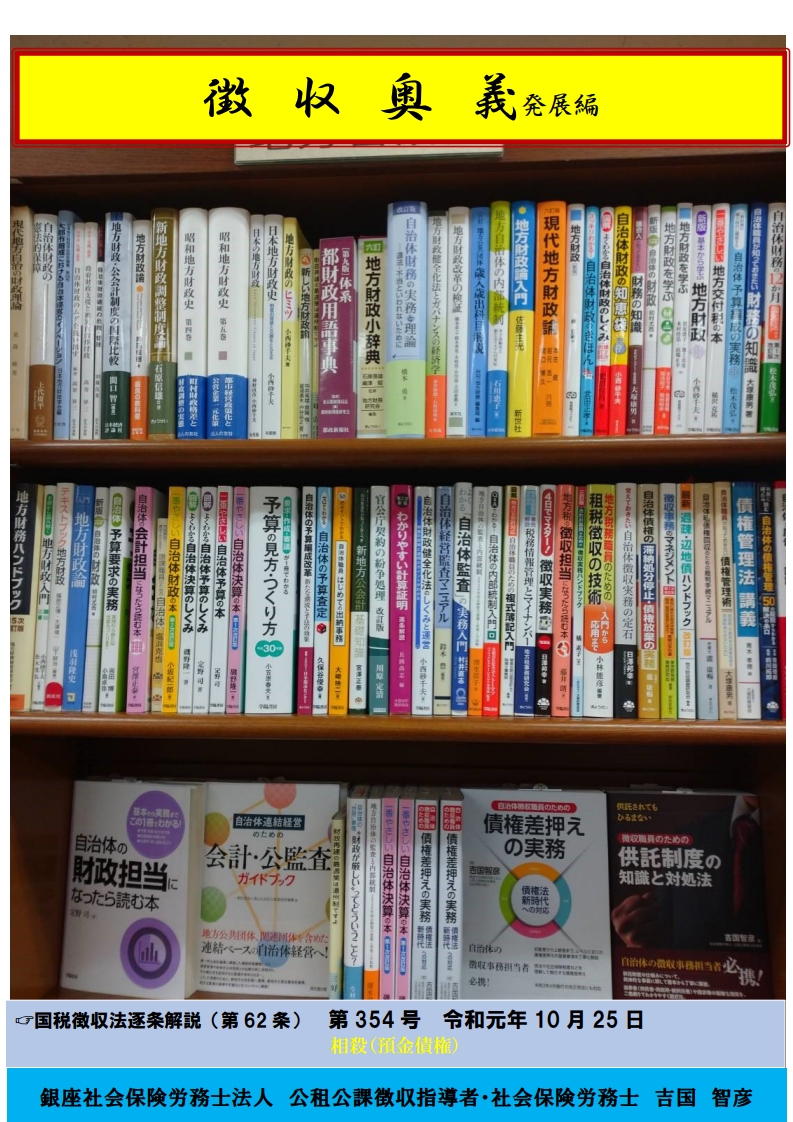
滞納処分の実務書:債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義353号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
債権差押通知書(差押調書・差押調書謄本)の取扱いや債権差押えにおける処分禁止効について解説しています。
ここでは、債権差押通知書の送達が重要となり、それが不十分であったたために取立権の行使において問題が生じた判例を紹介しています。
また、債権差押えとは、どういった性質のものか正確に理解しておくことが重要となります。
主な内容と判例は次のとおりです。
1 初めての債権差押え
2 債権差押通知書
3 差押調書及び差押調書謄本
4 滞納者に対する処分の禁止
5 債権証書の取上げ
6 債権差押えの効力
7 履行の禁止
8 差押えの相対的無効と手続相対効
最三判昭48.3.13(民集27-3-344)
最三判昭55.1.11(民集34-1-42、金法914-126)
東京高判昭53.7.19(民集34-1-57、判時902-59)
東京地判昭52.2.28(民集34-1-50、金商595-8)
最二判昭40.11.19(民集19-8-1986、判時434-33、判タ185-86)