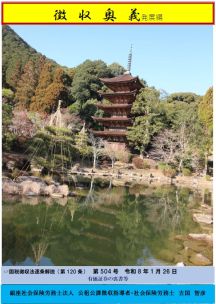滞納処分の実務書:預金債権の差押え
- カテゴリー
- 徴収奥義
徴収奥義346号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
目次の更新をしました。
通常は、預金名義人A=預金債権者Aである。しかしながら、預金名義人はAであるが、預金債権者はBであるということがあります。定期預金債権では、客観説との判断基準があるところ、その理論にあてはまらず複雑な諸要素を総合判断すべきことが求められます。
判例の考察を抜きにして預金債権の差押えをすることはできないといえます。重要な判例を図解入りで掲載しており、腕のよい徴収職員となるためには重要な知識となります。
主な内容と掲載判例は次のとおりです。
1 無記名なるもの
2 預金債権の帰属認定一般論
3 客観説・主観説・折衷説
4 預金についての基本通達の解釈
5 預金債権判例の構成図
6 預金債権判例の系譜
7 預金債権差押えおける帰属認定の判断基準
8 普通預金債権の帰属認定事
9 犯罪収益移転防止法との関係
10 預金債権帰属認定の新判断基準
掲載判例
最一判昭32.12.19(民集11-13-2278)
最三判昭35.3.8(集民40-177)
最三判昭48.3.27(民集27-2-376)
最二判昭52.8.9(民集31-4-742)
最三判昭57.3.30(金法992-38)
最二判平15.2.21(民集57-2-95、金法1677-57)
最一判平15.6.12(民集57-6-563、金法1685-59)
東京地判平6.7.29(金法1424-45)